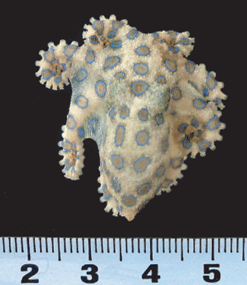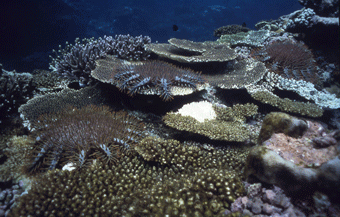|
|
|
|
食品衛生化学研究室
ご承知の通り,これらの生物にはいろいろな物質が含まれています。恩恵のひとつとして食糧資源としての役割が挙げられます。食料として摂取したときに栄養成分,機能性成分といった「プラス思考」の作用をもたらす物質の反面,有毒・有害成分といった「マイナス思考」の作用を持つ物質も少なからずあります。
食品衛生化学研究室では,後者の範疇に含まれる物質を食料という領域を飛び越えて化学的手法により安全性という側面で研究しています。具体的には次の3つの大きなテーマに取り組んでいます。
|
|
|
卵を食べたり牛乳を飲むと,じんましんやぜんそくなどのアレルギー症状が一部の人に引き起こされます。エビ,カニや魚類,魚卵,貝類など魚貝類を食べたときにも人によっては同様のアレルギー症状が現れます。
本研究室では,魚貝類中のアレルギーを引き起こす原因物質(アレルゲンと呼ばれ,普通はタンパク質です)の本体を突き止め構造を明らかにすること,構造とアレルギー発症との関連を明らかにすることなどを目的に研究を行っています。
また,魚類に寄生する寄生虫(たとえばアニサキス)もアレルギーを引き起こす原因であることが知られ,魚が原因と思っている人の中に実はアニサキスが原因だったという事例も少なくありません。本研究室ではアニサキスのアレルゲンについても研究しています。
アレルゲンの諸性状を調べることにより,患者さんの診断,治療に役立つ情報とか,魚貝類を材料とする低アレルゲン化食品の開発のように食品産業のための重要な知見が得られます。
海の中では,獲物を捕まえるときや逆に敵の攻撃から逃れるとき,あるいはなわばり争いのときなど,生存競争に打ち勝つために毒を使っている動物がたくさんいます。海洋動物にとっての本来の役割とは別に,フグ毒のように食べて危ない毒,クラゲ毒やイソギンチャク毒のように刺されて危ない毒は,あまり好ましくない面で人間生活とも深く関わっています。
本研究室では,刺されて危ない毒(イソギンチャク毒,オニヒトデ毒)を中心として,魚の体表粘液に含まれる毒,肉食性巻貝やイカ・タコの唾液腺に含まれる毒などの性状を調べています。
普段口にすることがない海洋動物も研究対象として取り上げていますが,毒成分の性状を明らかにすることは公衆衛生上欠くことのできない研究ですし,「毒を制して薬となす」といわれるように,毒成分の特殊な性質が薬に活かされることだってあるかも知れません。
|
|
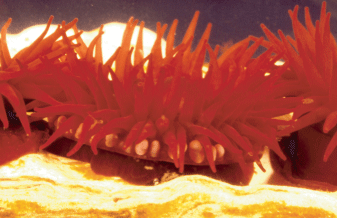 |
| ウメボシイソギンチャク |
ヒ素だとかカドミウムなど聞いたらゾッとするような元素が,人為的な海洋汚染が原因ではなくて,われわれが普通に食べている魚貝類や海藻の中に高濃度に含まれています。しかし,なぜか昔からこのような有害元素による中毒例はありません。その理由は有害元素がどのような化学形で存在するのかによります。
一方,食品加工中にあるいは食べてから何らかの代謝を受けて毒性が強まるとしたら危ない話ですよね。本研究室では海産物中のこれら有害元素に関する研究も行っています。
海産物あるいはそれらの加工品中に有害元素が含まれていても,その化学形や毒性・代謝の研究により安全性が説明できれば,日常食べても問題がないといえます。