黒潮大蛇行の形成に果たす膠州海山の役割
日本の南を流れる黒潮には、四国から本州の南岸に沿ってまっすぐに流れる「非大蛇行流路」と、紀伊半島の沖で南へ大きく迂回して流れる「大蛇行流路」という二つの安定した流路(流れのパターン)が存在します(図1)。 これは、湾流などの他の西岸境界流には見られない、黒潮だけの大きな特徴です。 非大蛇行流路も大蛇行流路もともに、一旦形成されると多くの場合、一年以上の長い期間にわたり安定して持続します。 これに対して、非大蛇行から大蛇行への遷移は半年以下という短い期間で行われます。
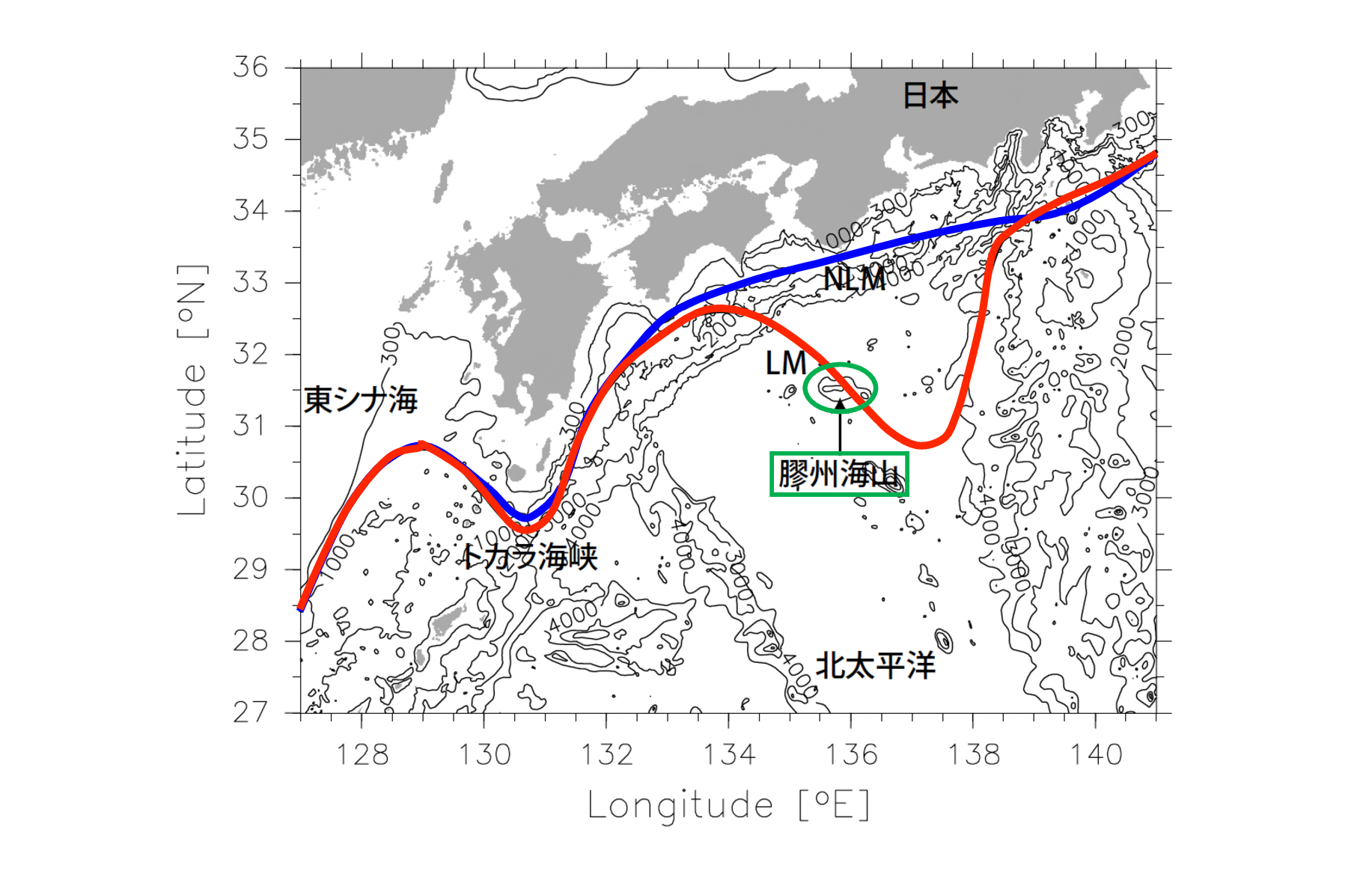
図1: 日本の南岸における黒潮の流路。青線:非大蛇行流路。赤線:大蛇行流路。緑線は膠州海山を表す。
非大蛇行流路から大蛇行流路への遷移は、九州の南東沖で黒潮に渦が衝突することで発生する小さな蛇行(小蛇行)が引き金となって生じます。 発生した小蛇行は黒潮に乗って徐々に下流へと流されて行きます。 そして、紀伊半島の沖までやって来た後に急速に発達することで大蛇行へと遷移していくことが、近年の衛星観測によって明らかになってきました。 このとき、小蛇行の急発達はちょうど「膠州海山」(図1の緑線)上を小蛇行が通過する際に生じることから、黒潮の非大蛇行流路から大蛇行流路への遷移にはこの小さな海山が重要な役割を果たしている可能性が指摘されるようになってきました。
ところが、一体なぜ膠州海山のようなローカルな海底地形が大規模な黒潮の流路をコントロールできるのか、そのメカニズムは不明なままでした。 そこで私たちは、力学過程の解析が簡単な、非常にシンプルにした数値モデルを用いて、この「海山効果」を詳しく調べました(図2)。
図2ではコンターが黒潮の流れ、緑線が海山を表しています。 左のように日本の南に海山を置いた場合には、上流から伝播してきた小蛇行が海山上で急発達するのに対して、右のようにこの海山を取り除いた場合には、上流から同じように小蛇行が伝播してきても、十分に発達せずに東へと流れ去ってしまいます。 このように、簡単な数値シミュレーションによって海山効果を実証することができました。
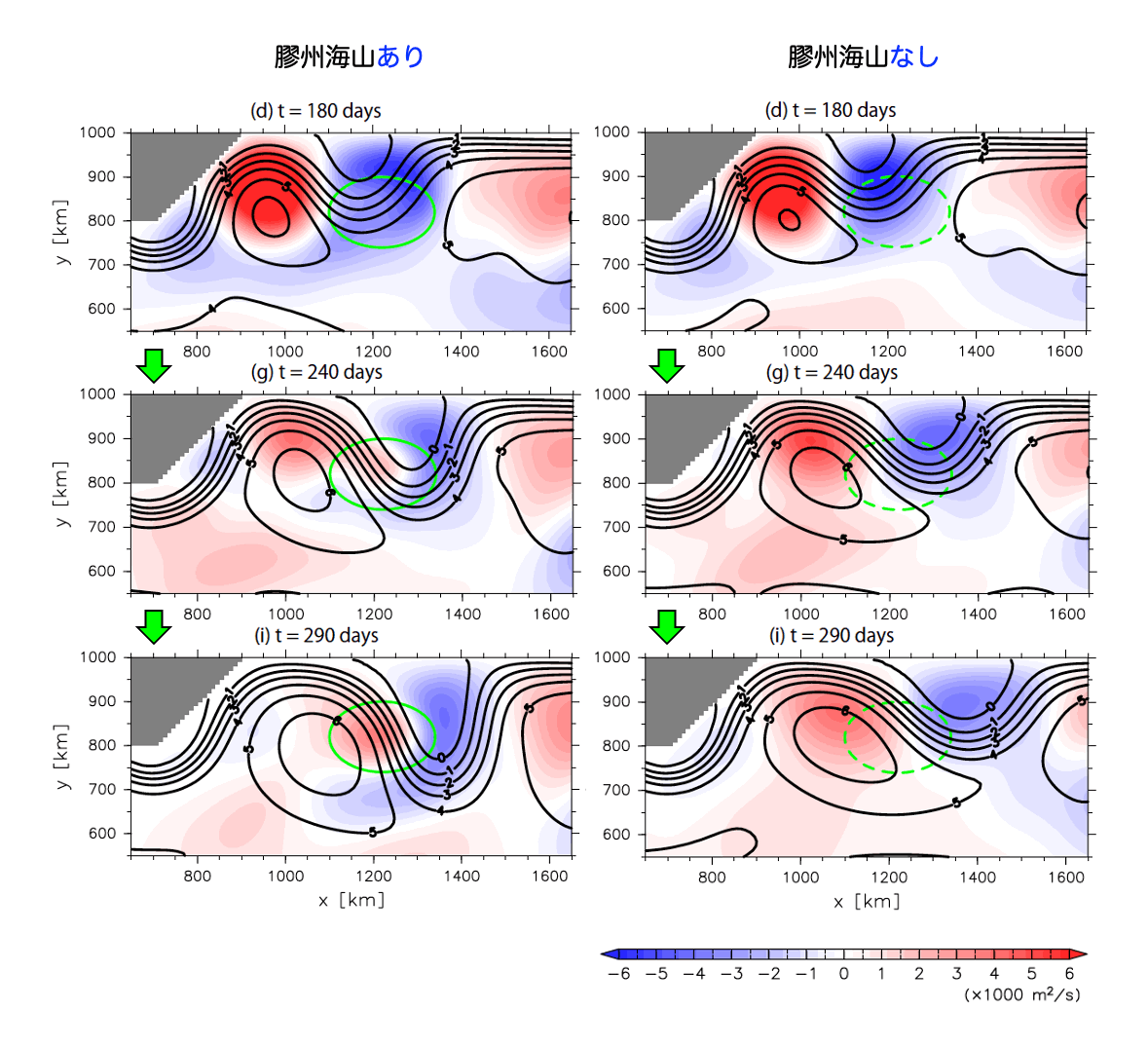
図2: 数値モデルで再現された黒潮の非大蛇行流路から大蛇行流路への遷移過程。左が海山あり、右が海山なしの場合のシミュレーション結果。コンターが上層の流れ(すなわち黒潮)、カラーは下層の流れを表す。緑線は海山を表す。
さらに、簡単な理論的解析の結果、海山を置いた場合には、ちょうど小蛇行と同じくらいのスケールで擾乱の成長率が高くなり、これが小蛇行から大蛇行への遷移を引き起こすことがわかりました(図3)。 さらに詳細に調べたところ、この高い成長率は、上層のロスビー波と下層の海山捕捉波とが結合することによって海山上で強化された傾圧不安定(地球の大気・海洋中で最も普遍的な不安定の一つで、大気の温帯低気圧が発達するメカニズム)に起因するものであることが示されました。
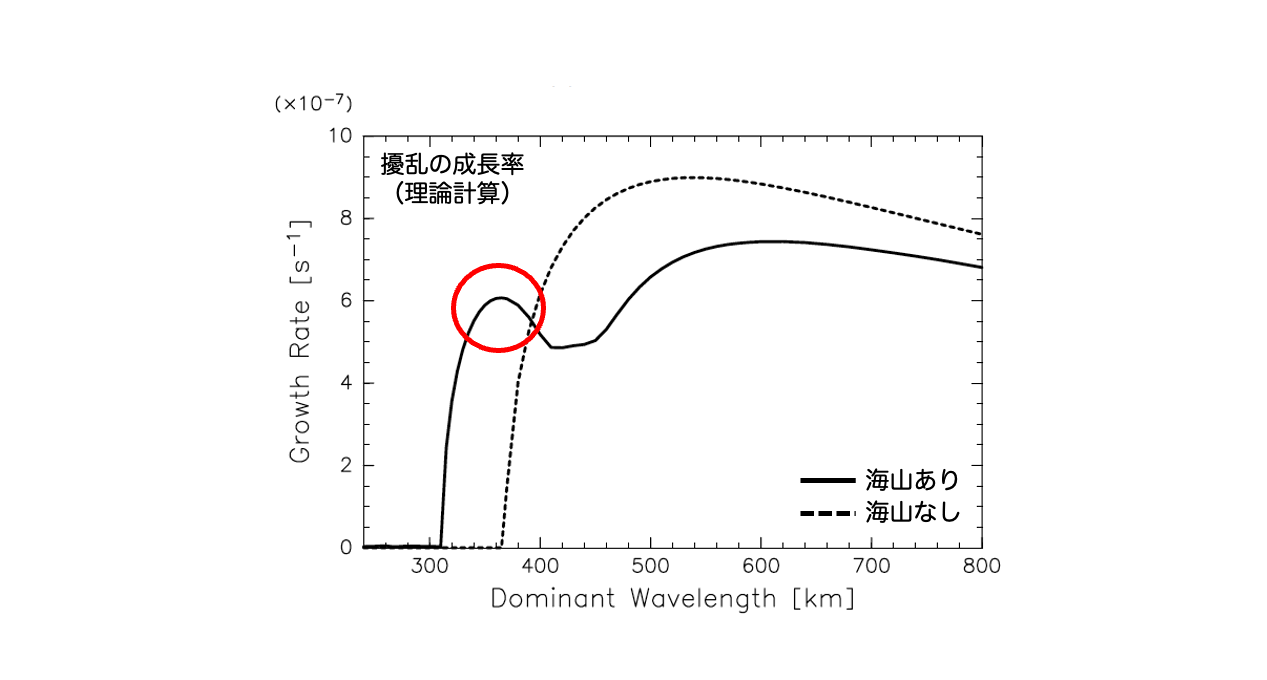
図3: 理論的に求めた擾乱の成長率。波長の関数としてプロットしている。実線が海山あり、破線が海山なしの場合。海山ありの場合にだけ、小蛇行のスケールに当たる波長320~400 kmで成長率のピーク(赤丸)が表れていることがわかる。
ホームへ