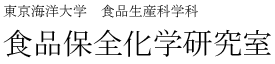
教授 : 和田 俊(わだ しゅん)

研究経歴等
| 年月 | 職名 | 研究概略 |
| 〜昭和48. 〜 |
米国ニュージャージー州立ラトガース大学・大学院留学(Reserch Associate) | 食品、特に脂質のフレーバー化学およびその機能化学に関する研究をStephen S.Chang教授(アメリカ油化学会会長)の下で行う。 |
| 昭和49.11 〜 |
東京水産大学助手 | HPLCによるトリグリセリド分子種分析を世界で始めて行い、その分離因子を見出した。この因子をパーティションナンバー(PN)と最初に命名して定義し、その分析手法を確立させた。 |
| 昭和57.10 〜 |
東京水産大学助教授 | |
| 昭和59.11 〜 |
ニュージーランド科学技術省(DSIR)客員研究員 | 水産食品中の脂質劣化機構に関して抗酸化剤の作用メカニズム等を魚油で行い、ローズマリーとトコフェロールが抗酸化相乗作用を示すことを明らかにした。 |
| 平成3.3 〜 |
文部省甲種在外研究員(米国およびスウェーデン) | 魚油由来のにおい物質の生成について、米国・ウイスコンシン大学食品学科客員教授として、大学院生の指導を行うと共に、スウェーデン・ルンド大学環境化学科客員教授としても、脳機能に関与するスフィンゴミエリンのHPLCによる脂質分子種分析法を確立した。 |
| 平成8.6 〜 |
東京水産大学教授、現在に至る。 | |
| 平成13.3 〜 |
文部科学省短期在外研究員 (アイスランド大学) |
魚油特有のDHAとその酸化劣化安定性がトリグリセリドのβ位に有することを解明し、これら高度不飽和脂肪酸含有の水産食品の機能優位性を明らかにした。 |
| 平成15.10 〜 |
東京海洋大学教授(大学名改変による) この間、大学院応用生命科学専攻主任および食品学科長、食機能保全学専攻主任等を歴任、現在に至る。 |
一連の研究成果の多くは、国際的な学会誌をはじめ教科書「食品機能学-脂質-」(丸善発行)等の学術著書にまとめられている。 この間、脂質劣化と分子種分析等の研究のみならず、世界の食品規格基準であるCodexの日本政府初の申請である「即席ラーメンの基準制定」に日本政府代表団の技術代表として各国際会議に出席し、技術面からその制定に貢献した。 |
受賞歴・表彰歴
■平成21年9月 日本油化学会・エディター賞受賞(Journal of Oleo Sience Editor's Award)(Metabolism of Odd-numbered Fatty Acids and Even-numbered Fatty Acids in Mouse)
■平成18年3月 日本油化学会・学会賞受賞(天然の脂質分子種分析および食品の脂質機能性保全に関する研究)
■平成17年9月 日本油化学会・エディター賞受賞(Journal of Oleo Sience Editor's Award)(Quantification Method for Triacylglyceride Molecular species in Fish Oil with High Performance Liquid Chromatography-Ultraviolet Detector)
■平成14年9月 日本脂質栄養学会・ランズ学術賞受賞(脂質栄養のための油脂分子種およびn-6/n-3脂肪酸分析に関する研究)
■平成7年10月 日本油化学会・第33回討論会最優秀ポスター賞受賞(西都原古墳から出てきた脂肪酸)
■平成5年4月 アメリカ油化学協会・Outstanding Paper Presentation賞受賞(Prevention of Fish Lipid Oxdation by Synergistic Effect of Natural Antioxidants)
■昭和60年4月 日本油化学会/学会・進歩賞受賞(天然油脂トリグリセリドの分子種に関する研究)
これまでの研究成果等
(1)研究論文数 :134編(和文[国内]誌 41編、欧文[国際]誌 93編)
(2)著書・辞書・辞典:79冊
<最近数年間の主な著書(編集および分担執筆を含む)>
■新しい漁業のデザイン 第7章 沖合資源の品質-太平洋沖合域のサンマ加工素材としての特性-(恒星社厚生閣、2010)
■食品機能性の科学、第6章 多価不飽和脂肪酸、第16章 かつお節(産業技術出版、2008)
■サバがマグロを生む日(77p〜90p)旬の魚から長寿の”脂”を美味しくもらう(つり人社、2008)
■機能性油脂の展開(1p〜289p)第3章、執筆および全章の監修(シーエムシー、2006)
■機能性油脂のフロンティア(1p〜340p)執筆および全章の監修(シーエムシー、2005)
■食品機能学-脂質-(1p〜227p)第一章〜第十二章(丸善、2004)
■水産食品栄養学(1p〜128p)水産物の成分、色、ニオイ、味(執筆および全章の監修、2004)
■かつお節(1p〜108p)(幸書房) など
研究題目
① 食品脂質に関する研究
(魚介類トリグリセリド分子種分析とEPA,DHAの分布など)
② 脂質の酸化機構とその抗酸化に関する研究
(食品酸化でのにおい生成および天然抗酸化剤による劣化抑制など)
③ 水産物の有効利用に関する研究
(未利用資源の探索と食用資源および機能性素材への変換など)
研究課題への取り組み
主な研究課題は「天然脂質の分子種分析」であるが、これを基礎として同時に「水産物の有効利用および食品の脂質劣化機構とその機能性保全などの諸問題について」の一連の研究を行なっている。天然油脂の分子種組成分析を高速液体クロマトグラフィー(HPLC)により世界で最初に手がけ、その後多くの脂質関連分野でこの分析手法が通常に行われるようになった。この基盤研究により、脂質の構造と成分組成の把握が容易になり、食品脂質機能保全およびその利用化学分野の進展に寄与している。
すなわち、上述の「天然脂質の分子種分析」では、世界に先駆け、天然脂質のトリグリセリド(TG)分子種分析をHPLCで行い、その分離がTGのアシル基の総炭素数と二重結合数に起因するパーテイションナンバー(PN)によることを明らかにした。つまりHPLCによる脂質分子種分析の概念がはじめてここで確立された。この考えは現在、脂質の分子種分析で常用されており、PNは世界の共通語として使用され、ガスクロマトグラフィー質量分析(GC-MS)、HPLC-質量分析(LC-MS)などの脂質の機器分析への応用展開に活用されている。さらに、生理機能を有するイコサペンタエン酸(EPA)やドコサヘキサエン酸(DHA)の劣化は食品中で容易に起こることから、その分析手法と精度および迅速性が重要である。そこで、従来のGCによる方法のみならず、プロトン-核磁気共鳴法(NMR)およびカーボン-NMR法により、それぞれn-6系脂肪酸とn-3系脂肪酸の存在比率およびTG内のEPAとDHAの結合位置を容易に分析する方法を提唱し、その分析法の公定化に尽力し、基準分析法として確立した。
これら一連のTG分子種組成解析の進展により、TGの構成脂肪酸種の結合位置が推測できるようになり、脂肪酸結合位置と生体内吸収との関係を明らかにする研究として発展している。分子種組成の考え方は、生理活性機能発現のためのTGのβ位結合DHAや意図する必須脂肪酸結合の生体内における効率的吸収などの観点から、いわゆる「構造脂質」の概念と密接に関連し、この基礎事項として重要である。
魚油に多く含まれるEPAやDHAは、生活習慣病予防の観点から、現在大きな注目を浴びているが、酸化劣化しやすく、食品に利用しにくいという大きな欠点を有する。そこで天然脂質の機能性保全についての研究も重ね、天然物質の抗酸化性の研究では、ローズマリー抽出液とトコフェロールを併用した抗酸化剤の系を用いて、魚油に対して強い抗酸化相乗作用があることを見出した。これらに関連するにおいの変化についても食品保全の立場から研究している。天然脂質の季節変動や脂質成分と機能性などについて、TG分子種分析を基盤とした総合的研究により、各種魚介類脂質の組成および脂質の蓄積性推移などを明らかにし、食品脂質の基礎的および応用的諸問題の解明に努力している。
食資源としての水産物の利用を安全・安心の下に積極的に推進し、世界の貴重な海資源を活用することで、人々の健康と豊かな暮らしに貢献したいと考えている。
趣 味
テニス(USPTA公認国際指導員)、はがき絵、音楽
TOP / 研究室概要 / 写真
東京海洋大学 食品生産科学科