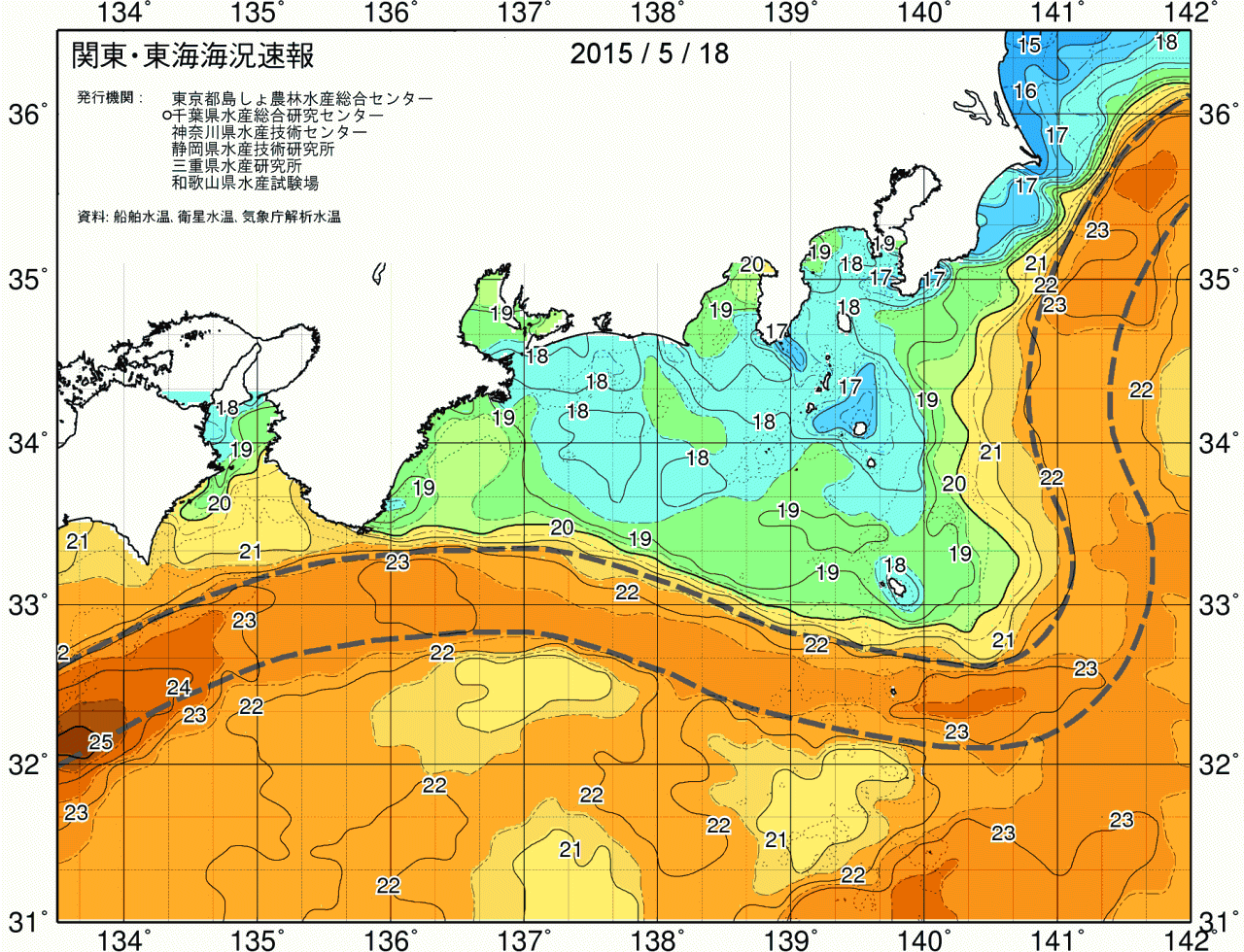
2015�N�x�@�C�m�w���K�U
LEG B 5��25���i���j�`29���i���j
�ϑ��f�[�^
CTD�f�[�^�F�_�E�����[�h
ODV3.4�\�t�g�E�F�A�F�_�E�����[�h
�h�C�c�E�A���t���b�h�E�F�Q�i�[�ɒn��������Ocean Data View �iODV�j�\�t�g�E�F�A�Ή��iver3.4�j�̌`���ɂ��Ă��܂��B
ODV�̎g�����́A2008�N�x�u���V�X�e���Ȋw���K�i�p�~�Ȗځj�v
�����V�X�e���Ȋw���K�@�㔼�D���������������������B6�y�[�W�ȍ~�̕����ł��B
�����̉��K�ł́ACTD�ϑ��������̐����T���m���[�^�\�ɂĕ��͂��������ōZ��������@��������Ă��܂��B
�܂��AWOCE�iWorld Ocean Circulation Experiment�j�̃f�[�^�A�k�ɊC�̃f�[�^��p���āA
���E�̊C�̂ǂ��Ő[�w�����`�������̂��H�A�C�m�͊w���x��i�n�t��/�C�m�z��j�Ȃǂ̍쐬�A
�ȂǁA���g�Œ��ׂ�ۑ���o���܂����B
�ϑ����ԑO��̏�
�@�@�@�@�@�@�@5��18������6��1���܂ł̊C�ʐ����̕ω��i�N���b�N�Ŋg��j
���\�A�ʔ����u�Ԃ𑨂��Ă����ȂƁA�v���܂��B
�C�m�w�̎��K�Ƃ��āA�����A���w�A�����̗l�����A�����Ă���A
���̂܂܂̊C��������̍ŗǂ̎������ł�����!
���B�剫�ɂ������␅��i�Q�j���藣����A���M�яz�Ɏ�荞�܂�悤�Ƃ��Ă��܂��B
���v���̈��M�яz�ɔ����v���̉Q�i�x�j�����肱�ނ��Ƃɂ���āA���M�яz��
���܂肷���Ȃ��悤�ɒ��߂���Ă����̉ߒ��ł��B���q���̍��������ł́A
���M�яz�ɂ��鐅�i���v���̉Q�x�j�������яz�ɁA
�����яz�ɂ��鐅�i�����v���̉Q�x�j�����M�яz�Ɏ�荞�܂�邱�Ƃɂ���āA
����A�o�[�^�[������s���Ȃ���A���M�яz�A�����яz���\�����Ȃ��悤
�����t��Ԃ�ۂƂ��Ƃ��Ă��܂��B
�ʂ̌���������A�֍s�����̓����g�����Z���Ȃ�A���Ɉړ����Ă��܂��B
����ɂ́A���X�r�[�g�̐������֗^���Ă���A�g���̒Z���g�قǁA���֓`�d���鑬�x��
�������Ȃ邱�ƂɈˑ����Ă��܂��B
�C�m���̗͊w��C�m�����̍u�`�ł��̂�����̎d�g�݂ɂ��Ă͐��������Ǝv���̂ŁA
�����̂���w���́A�ǂ����B
Leg B�@�ϑ����i5��26���j�̏iSt.1-St.7�̊ϑ��_�͗\��ʂ���s�j�@-- �N���b�N�Ŋg��
�@2015�N5��26���̊C�ʐ������z�Ǝ��{�ϑ��_�@�@�@�@�@�@Chl-a�Ǝ��{�ϑ��_�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@Chl-a���͘p�E�����p�t��
St.2
�ł̃N�����t�B���A�h�{����St.3�ȍ~�Ƒ傫���قȂ��Ă������Ƃ��[���ł��܂��ˁB
�����̎֍s�Ƃ��������A�֍s���Q�ɂȂ�ASt.4�܂ł͓�����̗���ɂȂ��Ă������Ƃ�������܂��B
St.2�ő�����ꂽ���́A�O�m�̕ω����p�̐�����������o�����I
���̏u�Ԃ𑨂��Ă������Ƃ��ǂ�������܂��B
�����N�FPPT
Leg B�@�̌v��i�����܂ōD�V�̏ꍇ�̈āj
���s���\��(word�t�@�C��)�A���ύX�āF�s���\��(word�t�@�C��)�i5/21up�j
���ϑ��_�}�b�v�i�}�b�v���N���b�N����ƁA�傫�Ȑ}���J���܂��j
�@2015�N5��18���̊C�ʐ������z�Ɨ\��ϑ��_�@�@�@�@�@�@�C��n�`�Ɨ\��ϑ��_�@�@�@�@�g�Q�\��i2015�N5��21��03�F00�������l�Ƃ����\��j