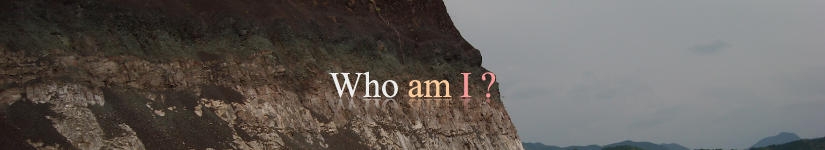![]()
生命の誕生とその後の進化
もともと化石少年で、化石採集と天体写真が趣味だったため、大学では地質学科に。当然地質学科には天文はないので、化石の研究をしようかと思いましたが、固有名詞を覚えるのが苦手だったため(人の顔と名前も一致しない...)化石研究には見切りをつけ、化学的証拠から生命の起源を探る研究に取り組みたいと今まで右往左往してきています。地球の初期環境と初期生命は互いに相互作用しながら、進化してきました。その道筋がどのようなものだったか解明していきたいと妄想しています。
現在進行中及び興味のある研究課題
微生物が支える生態系に関する研究:安定同位体やバイオマーカーを用い、様々な環境(海底熱水系、冷湧水系といった深海から、海底に沈んだクジラ遺体周辺、さらには干潟や土壌中まで)中から微生物を栄養源とする生態系がどの程度広がっているか明らかにする。この研究は、微生物のみから構成された生命誕生初期の地球から、より高度な生物が発生してきたときの生物進化に関する情報を提供してくれるものと期待している。
化石生物の栄養生態に関する研究:上記研究を化石生物にまで発展させた研究。貝殻や骨化石から抽出した有機物などを用いて、その栄養源や生態を明らかにする。
海底熱水系に分布する有機物に関する研究:高温(>300℃)の熱水を噴出する海底熱水系では周辺の有機物が急速に変質し石油によく似た炭化水素が生成したり、熱水中に溶存する化学成分に依存した微生物群集が生産する特異な有機物が蓄積している。また、海水が地殻に染みこみ熱水として湧出する循環過程で海水中の溶存有機物が変質し、海洋の炭素循環になんだかの影響を及ぼしていることが期待される。この様な、熱水活動に絡んだ有機地球化学的な課題に興味がある。
鹿児島湾若尊(わかみこ)海底火山に関する研究:桜島の北東の海底に活火山があり、激しい噴気活動と熱水活動が起こっている。ここは、上記3の研究の主な舞台の一つであると共に、活火山である本海域に興味がある。火山としての規模や活動度に関する総合調査を企画したい。
どんなことをやってきた?
学生時代は、干潟の堆積物表層で起こっている硫黄の物質循環を硫黄同位体比をトレーサーに追跡する研究を行っていました。博士課程以降、海底熱水活動域の生命活動に関する研究に取り組み始め、鹿児島湾若尊熱水系における熱水性石油の発見、有機成分や生物の親生元素の同位体を使った研究を行っています。その他、有機成分を使った古気候の復元や過去の生物の生態に関する研究もやっているつもりです。
福岡県北九州市生まれ。九州大学理学部地質学科卒業,同大学大学院理学研究科地球惑星科学専攻博士課程修了。博士(理学)。日本地球化学会、日本有機地球化学会、日本ベントス学会、American Geophysical Unionの正会員。血液型はO型と思われる。
 HOME
HOME Event
Event Photo
Photo Staff
Staff Link
Link 環境科学科Top
環境科学科Top Member Only
Member Only