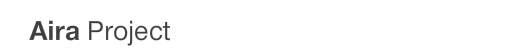有光層内の化学合成生物群集
水深90mに生息するハオリムシ類
火山が育む生命
 1978年にガラパゴス諸島沖合で熱水噴出孔とそれに群がる多数の”奇妙な”化学合成生物が発見されて以来、火山国であり、潜在的に化学合成生物の存在の可能性が高いと期待される日本でも化学合成生物の探査が活発に行われました。これらの生物の多くは水深600m以深と、いわゆる深海域に生息していたのですが、鹿児島湾では深くても200mという水深にもかかわらず、化学合成生物の一種であるサツマハオリムシが見つかっています。そもそもが、漁師さんの網にチューブに入ったヘンな生物が捕れたことがあるとか、海底火山の調査の過程で行った海底曳航カメラの映像にヘンな生物が映っていたというのが、本海域でのハオリムシ群集発見のきっかけです。海底火山活動により、活発な噴気活動が知られていた本海域では、当然ながら熱水活動もあるものと期待され、化学合成生物の存在が取りざたされたようです。
1978年にガラパゴス諸島沖合で熱水噴出孔とそれに群がる多数の”奇妙な”化学合成生物が発見されて以来、火山国であり、潜在的に化学合成生物の存在の可能性が高いと期待される日本でも化学合成生物の探査が活発に行われました。これらの生物の多くは水深600m以深と、いわゆる深海域に生息していたのですが、鹿児島湾では深くても200mという水深にもかかわらず、化学合成生物の一種であるサツマハオリムシが見つかっています。そもそもが、漁師さんの網にチューブに入ったヘンな生物が捕れたことがあるとか、海底火山の調査の過程で行った海底曳航カメラの映像にヘンな生物が映っていたというのが、本海域でのハオリムシ群集発見のきっかけです。海底火山活動により、活発な噴気活動が知られていた本海域では、当然ながら熱水活動もあるものと期待され、化学合成生物の存在が取りざたされたようです。
ところで、これまでの我々の長い調査の歴史(といっても8年くらいですが)で姶良カルデラ内で熱水活動が確認されているのは若尊火口と呼んでいる水深200mの凹地内です。しかし、ハオリムシ群集が発見されているのは、その凹地の直ぐ東にある海丘上で、しかも、その海丘のてっぺん、水深100〜80mの領域です。この群集の近傍には火山噴気ガスは多数見られますが、どんなに探しても熱水の兆候は得られませんでした。火山ガスの温度が周辺の海水温より高いという報告もありますが、熱水はありません。また、ハオリムシ類は化学合成のエネルギー源に硫化水素を利用します。噴気ガスの中には体積比で最大5%程度の硫化水素が含まれていますが、これは火山起源主のです。ところが、サツマハオリムシの硫黄同位体組成を調べたところ、ハオリムシの利用する硫化水素は硫酸還元細菌が海水中の硫酸を還元して作る硫化水素であることを示しました。
この海域の噴気ガス中には、硫化水素の他にメタンが多量に(体積比で最大5%)含まれていました。ここで思い浮かぶのが、熱水ではなく、冷湧水系の生物群集です。火山などの熱源がない日本海溝や南海トラフといった海溝の陸側海底にもハオリムシ類など化学合成生物群集が発見され、冷湧水生物群集と呼ばれていました。これらの生物は堆積物深部から湧出してくるメタンに富んだ流体をそもそものエネルギー源として成育しています。ここに住むハオリムシやシロウリガイの直接のエネルギー源は硫化水素ですが、メタンを使って硫酸を還元する微生物群集(硫酸還元細菌とメタン酸化アーキア(古細菌)のコンソーシアム)がこの硫化水素を供給しています。この様に、一義的にはメタンで駆動される生態系です。ですから、冷湧水生物群集とは厳密に言えばメタン湧出に支えられる生態系と言えます。
ということで、姶良カルデラでも同じ事が起こっており、噴気中のメタンを一次エネルギー源として、微生物による硫酸還元が起こり、発生した硫化水素がサツマハオリムシ群集を支えていると考えられるわけです。
以上のことから、ここは熱水生態系と考えられていましたが、厳密にはメタン湧出に支えられた生態系と言えます。本当は火山ガス中のメタンは普通はppmオーダーでしか含まれないのに、ここでは%オーダーで含まれるのはなぜか、という話もありますが、このメタンが世界でもっとも浅い海に住むハオリムシを支えている、すなわち、熱水ではないけども火山の恵みというわけです。
溝田智俊・山中寿朗(2003)深海化学合成生物群集から出現するベントスのエネルギー獲得戦略:軟体部の炭素、窒素および硫黄の安定同位体組成による解析.日本ベントス学会誌,58, p.56-69.
藤倉克則・山中寿朗・喜多村稔(2008)「深海調査船が観た深海生物 深海生物研究の現在」,分担執筆,2-2章 深海生態系―光合成と化学合成,pp.30-35,藤倉克則,奥谷喬司,丸山正編,東海大学出版会.
本文の無断転載はご遠慮下さい。