情報リテラシー 火曜4限
| ~1回目 ガイダンス~ | |
|
|
| ~2回目~ | |
|
|
| ~3回目以降~ | |
| Microsoft Word |
|
|
|
| 知財関連教育 | |
|
|
| Microsoft PowerPoint |
|
|
|
| Microsoft Excel |
|
|
|
| Microsoft Excel |
|
|
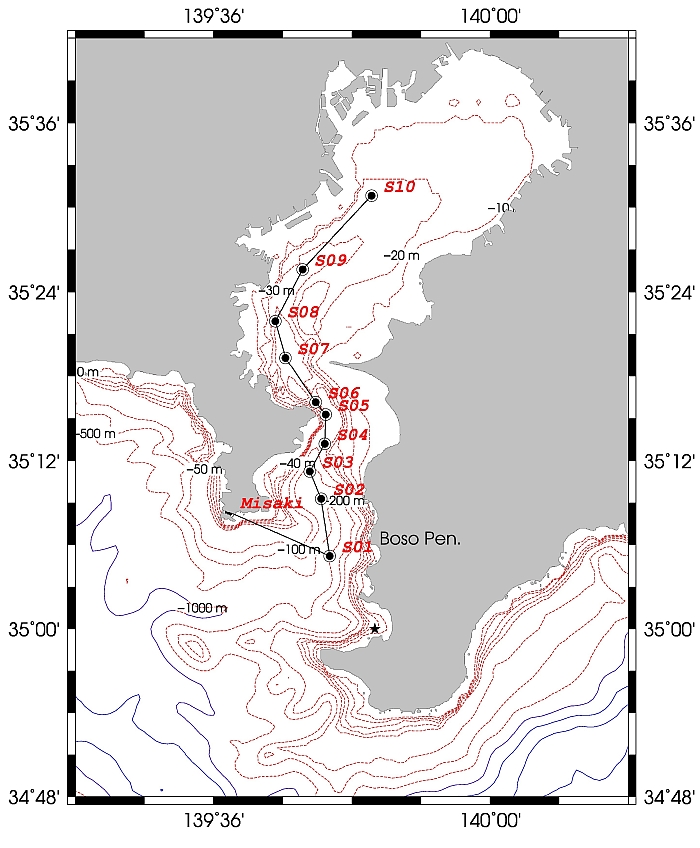 |
| Microsoft Excel |
|
| エクセルによる描画の限界を知り、海洋学ではどのようにデータを見るかを知る まずはエクセルでグラフを書く。 データはここからダウンロード 既存の観測データを用いて、作図。→ 鉛直プロファイル・散布図・断面図 1)各測点の水温・塩分などの鉛直プロファイルを書いてみる。 鉛直プロファイルなので、縦軸は深度、横軸が各パラメータということになる。 2)ある測線における断面図を書いてみる。等高線を使う。 データの善し悪しを調べてみる。→ 最小二乗法(エクセルの関数の中身を知る) →ODVフォーマットのデータ 次にOcean Data View(ODV)でいろんな海域の様々なデータを見る
|
|
| 昔ながらのウェブサイトの作り方:Hyper Text Markup Language(HTML) | |
コンテンツを選択するとメインウインドウで表示されるページが変わるようにできるようにする(リンクの張り方)。 あとは図表の説明をしておわり。 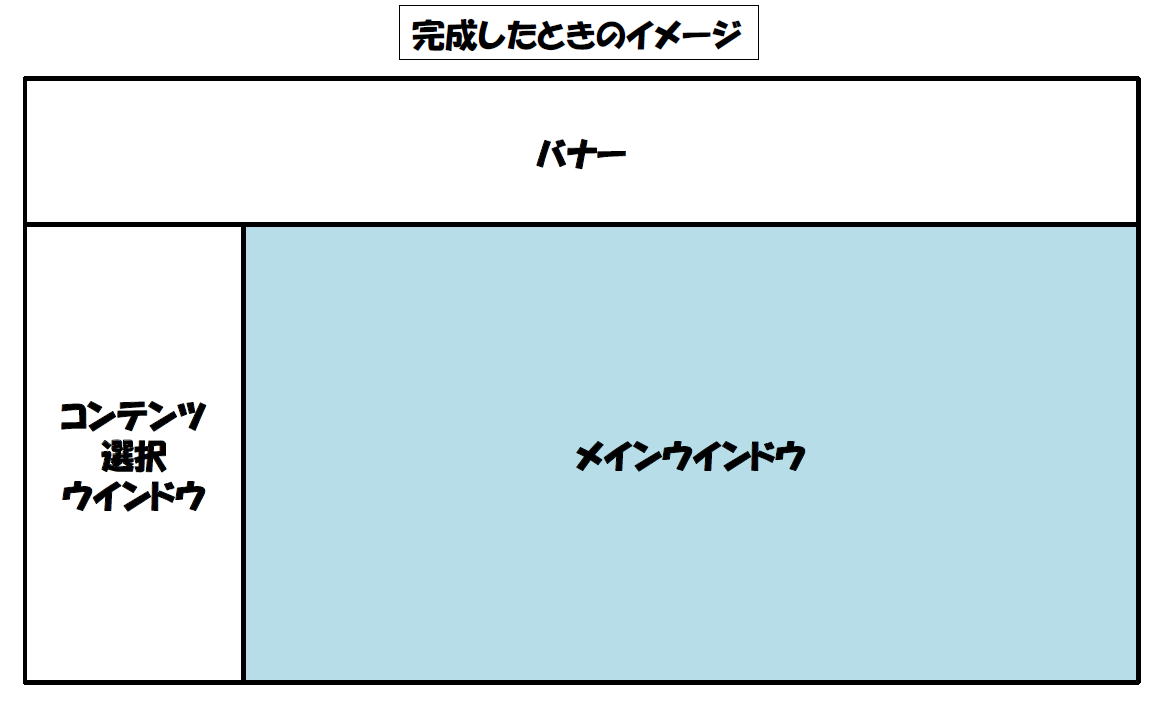
|
|